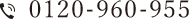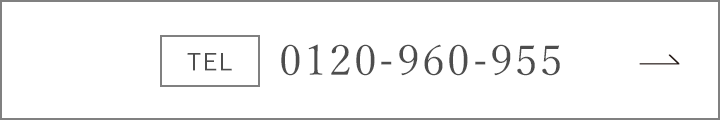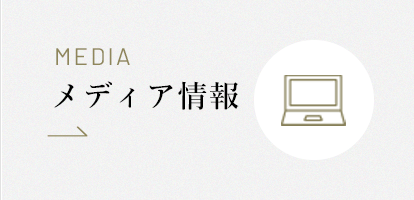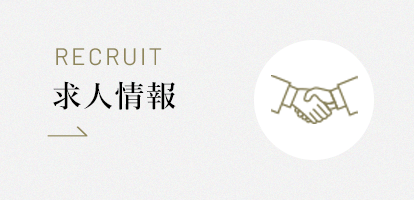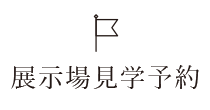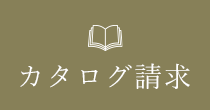2025/09/01
【防災の日】災害に強い家とは?家族を守る住まいの工夫

こんにちは、ベル・ホームです。
日本は「災害大国」と呼ばれるほど、地震・台風・豪雨など自然災害が多発する国です。近年は地球温暖化の影響で、ゲリラ豪雨による水害や土砂災害が増加し、被害も大きくなっています。
今日9月1日は「防災の日」。
改めて、家庭レベルでの備えや災害に強い住宅構造の重要性について知っていただきたいと思います。
備えるべき災害
日本では、特に被害が甚大であった災害を災害対策基本法において、「激甚災害」と指定しています。 令和7年9月現在、過去5年で主に激甚災害に指定されているのが、「地震」と「豪雨による災害」です。(参考:内閣府|過去5年の激甚災害の指定状況一覧)
そのため、ご家庭でも特に地震や水害への備え・対策は優先して行うと良いでしょう。
家を建てる土地選びも重要
災害への強さは建物の頑丈さだけでなく、家を建てる土地の強さも大きな影響を与えます。
国土交通省が公開している「重ねるハザードマップ」を活用すれば、地震による地盤の強さだけでなく、洪水や土砂災害に関する情報も把握できます。
家を建てる予定の土地を現地確認し、道路の陥没や周辺地域の塀に亀裂が入っていないかなどの確認も必要だといえるでしょう。
複数の情報源から得られる情報を照らし合わせることによって、災害に強い家づくりにつなげられるはずです。

居住地域の災害対策も知っておく必要があります。
これらの災害は、地域による影響も大きく受けやすいということも意識したいポイントです。
例えば海岸付近に住んでいる方は地震の際の津波などに特に注意しなければならない、川が近くにあるという方は豪雨の際の氾濫に注意しなければならないなど、災害のリスクが異なります。
起こる災害によって取れる行動も異なるほか、地域ごとに避難場所などが違うということもあるでしょう。
自身の居住地域で
● どのような災害リスクがあるか
● 避難場所はどこか
● どのような防災活動が行われているか
ということをしっかり確認しておき、万が一に備えておきましょう。

安全性が高い家が選ばれる可能性
自然災害が頻発している日本において、生命や財産を守るために自然災害に対する安全性の高い家への需要は高まっているといえます。
災害に強い家とはどのような特徴を備えているのかを解説します。
①災害に強い家
耐震構造・耐火構造がしっかりとしており、地盤が強く、定期的なメンテナンスが行われている住宅だといえます。
災害に強い家について考えるときは、家の形状・構造・材質・外壁・屋根などをしっかりと考えて設計する必要があります。
地域によって、頻発しやすい自然災害の種類はさまざまなので、予算と照らし合わせながら災害に強い家づくりを進めていくことが大切です。
施工予定地で想定される被害をハザードマップなどで事前に確認し、どのような家づくりを行うかを検討してみましょう。
②被災時も住める防災住宅の設備や間取り
万が一被災した場合、住み続けられる防災住宅としての備えも必要です。防災住宅のポイントは以下の3つです。
・生活用品や食料品を十分に備蓄できる
・避難しやすい動線が確保できている
・停電や断水に対応できる(太陽光発電・蓄電池、エコキュート、雨水タンク)
まず、生活に必要な日用品や食料を備蓄できるパントリーや納戸があることです。狭い住宅だとこれらを排除しがちですが、防災においては重要なスペースです。面積を確保できない場合は、床下収納庫などで代用しましょう。
また、2箇所以上から屋外に避難できるようにしておけば、万が一1箇所の出口が塞がれてしまっても避難が可能になります。特に、高齢者の方が住む住宅においてはできるだけ多くの避難経路を確保しておく必要があります。
そして、電気・水道などのライフラインが断絶した時の対策も大切で、自家発電できるシステムや雨水タンクなど最低限の水を貯蓄できる設備があると安心です。
日常に溶け込む「見えない防災」の工夫
防災というと、特別な設備を設けるイメージが強いですが、最近では日常に自然に溶け込む防災の工夫が注目されています。
平常時と災害時のフェーズをなくし、「いつも」の暮らしを豊かにするものが、「もしも」のときも役立ち、支えてくれるという考え方です。
住宅を建てる際必須ではありませんが、あればより安心できる防災設備をご紹介します。
▼パントリー

もともとは防災設備ではなく、日用品や食品を収納し、キッチンを美しく変えるためのパントリーは、備蓄品用のストックにも活用できるでしょう。
▼耐震ラッチ

耐震ラッチは、棚の収納扉が地震による振動で開いてしまわないよう、固定するための金具です。 普段はそのまま使用できますが、地震が起きた時に自動的に扉を固定してくれます。 地震の際には落下物による怪我も多いため、けが防止に効果的ですね。
▼埋め込み型の家具

見た目も間取りに合わせておしゃれな埋め込み型家具は、地震時に倒れることがないというメリットもあります。 大きな家具が倒れてしまい下敷きになったり、道をふさがれてしまったといった二次被害が防げるでしょう。
ウィズコロナ時代に役立つ“在宅避難”
コロナ禍で再注目されたのが「在宅避難」という考え方です。避難所に行かず、自宅で生活を続けられるよう備えておくことは感染症対策にもなります。
-
10日分の食料・飲料水の備蓄
-
医療機関とすぐ連絡が取れる体制
-
消毒液やマスクなど衛生用品の準備
-
家族それぞれが「一人になれる場所」を確保
精神的なストレスを減らし、長期の避難生活を見据えた工夫も欠かせません。
「災害に強い家」とは、単に頑丈な建物を指すのではなく、
災害を想定した土地選びや建物構造や素材の工夫、日常に溶け込む防災アイデアなどを取り入れた住まいのことです。家族の命と暮らしを守るために、ぜひ住まいづくりやリフォームの段階から“防災”を考えてみてください。
岡山県(岡山市・倉敷市・総社市・津山市・美作市)で新築・注文住宅・リフォーム・リノベーションをお考えの方は、地域密着のベルホームにご相談ください!